海原の平家伝説−奄美説話の原像−
 著:高橋一郎
著:高橋一郎三弥井書店・平成10年5月25日第1刷発行
四六版・P332・\2,800
この本は1994年に発行された「伝承のコスモロジー」の続編にあたります。「伝承の・・・」では、主に北大島(笠利・龍郷・名瀬)での伝承を聞き取り調査したものですが、「海原・・・」では南大島(大和・宇検・瀬戸内)での調査をまとめています。
「伝承の・・・」をまだ読んでない方は是非「伝承の・・・」を先に読んで下さい。
薩摩支配以前の沖縄との交流、それ以前の奄美に伝わる伝承、それを多い隠すように語られる平家伝説を綿密に調べています。
奄美では薩摩支配の始まったころにそれまで残っていた文書類がすべて焼き捨てられたため、薩摩支配以前の奄美の歴史というのが伝承でしか知ることができません。奄美を知らない方には史跡を見て廻るときの予習本として、知っている方も違う奄美の姿を見ることができると思います。
(水間)
(帯より)
”大和と琉球という異なる文化の重層する奄美。
そこに語り継がれた平家伝説とは・・・
その背後に隠された独自の伝承世界とは・・・
主要内容
海・山そして天空への眼差し
語り継がれた異人と豪傑たち
変奏する伝承と暮らし
暮らしの中の語り
伝承の拠点
伝承の行方
神祀るシマと人
伝承と歴史の隔たりと媒体"
 著:椿吉盛
著:椿吉盛私家版・1998年2月15日初版第一刷
A5変・P191・\1,200
「朝仁」というのは名瀬市中心街から赤崎をはさんで左に位置する町です。昔は農地が多く町の前の朝仁海岸は今の大浜海岸のように海水浴場としてにぎわっていました。
近年、長浜からトンネルがとおり名瀬市のベッドタウンとして隣の平松(小宿前の海を埋め立てて作られた町)ともに住宅地に様変わりしています。本書はその朝仁の昔のようすを伝え残すために著者がまとめたものを娘さんが発行しました。
(水間)
(帯より)
忘れられゆく”いにしえ”を未来に繋ぐ!
集落の小字名の由来から歴史・生活に至るまで、多岐にわたり詳細に探求した遺稿集
「・・・私たちがこれを手掛けようという気持ちになったのは、集落そのものが年々住宅が増加し、市街地化していくなかで、昔日の面影をとどめないまでに変容している現実を見直し、そのうえにたって、今のうちに資料を蒐集して記録を残さなければ、とりかえしのつかない空白をつくるという危惧の念をもったからである。」
本文「はじめに」から
 ゆらおう会・1998年4月30日
ゆらおう会・1998年4月30日B5版・P146・\1,800
島の料理の本というのは残念ながらほとんどありません。以前「シマヌジュウリ」という本があったのですが絶版になってしまい、新品はもちろん古本もほとんど手に入らないのが実情です。
そんななか「いじゅん川」の3号が島の料理の号を発行しました。
紹介されている料理は昔ながらのシマジュウリ(島料理)をはじめ、奄美の特産品を使った創作料理、食にまつわる話しなどです。執筆者は島のいろんな町の”おっかん”(お母さん)たちです。
この本を片手に島料理を作って食してみませんか。もちろん奄美でおっかんの作る島料理が一番ですが・・・
(水間)
 著:橋口実昭
著:橋口実昭南方新社・1998年9月1日第1刷発行
B5版・P214・\3,810
(表紙裏より)
心揺らす、生まれ島の記憶
永遠の時が、いまも流れる鹿児島県甑島列島。
それ故、破壊を唯一のエネルギーとする近代とは一線を画する独立した世界がある。
魚が群れ、藻が繁茂し、牛は草をはむ。
そして、そこに人が住む。
 編著:倉井則雄
編著:倉井則雄私家版・平成10年7月10日発行
A5版・P296・\1,800
奄美の方言についての本は専門書(言語学を研究する方が読むような本)はいくつかあるのですが、入門書となるとあまりありません。
この本では、島の方言についていろんな専門書などの書籍での説明をあげながら、著者の解釈・考えを加えて説明しています。その対象となる言葉はアマミの語源から始まり、用具・食べ物、挨拶と多岐にわたっています。
方言の入門書として一押しの本です。
(水間)
 著:中原ゆかり
著:中原ゆかり弘文堂・平成9年12月15日初版第一刷発行
A5変・P254・\5,900
(帯より)
生きた歌に会える!
隣近所や友人同士のちょっとしたおしゃべりが一段落すると、何となく三味線をとりだして歌遊びが始まる。雰囲気次第では真剣な歌い合いが夜中まで続く。人々の生活に豊かに生きる伝承歌謡のエスノグラフィー。
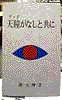 著:新元博文
著:新元博文あまみ庵・新書版・P61・\300
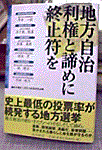 編:地方議員と市民の政策研究会
編:地方議員と市民の政策研究会南方新社・1998年11月1日第一刷発行
四六版・P179・\1,500
(帯より)
史上最低の投票率が続発する地方選挙
地方政治の担い手たちへの不信、そして諦め。
産廃、環境破壊、高齢化、教育問題・・・・
脅かされる暮らしと命を誰が守るのか。
- 序 章 貧困な地方政治の現状
- 鹿児島大学助教授 平井一臣
- 第一章 官僚制と地方政治
- 法政大学教授 五十嵐敬喜
- 第二章 情報公開制度
- 鹿児島大学教授 坂東義雄
- 第三章 産廃が田舎を襲う
- 佐賀県唐津市議会議員 増本亨
- 第四章 地方議会体験記
- 鹿児島県隼人町議会議員 続博治
- 終 章 政治の扉を開けよう
- 鹿児島県加世田市議会議員 平神順子
 編:財団法人 鹿児島県環境技術協会
編:財団法人 鹿児島県環境技術協会南日本新聞社・平成10年3月31日
A5版・P215・\1,905
(帯より)
鹿児島の自然遺産をまるごと一冊に!
国指定から県・市町村指定まで167の天然記念物ガイドブック
鹿児島の天然記念物の全てを網羅した始めての書物。
冷温帯から亜熱帯、火山から珊瑚礁まで幅広い自然を持つ鹿児島。
そこに、国、県、市町村で守ろうと決めた天然記念物がきらめいている。
それらは、人類の来し方を映し、人類の将来を占うリトマスともなる。
いざや人類との共存に思いを馳せん。
鹿児島県立短期大学学長 田川日出夫