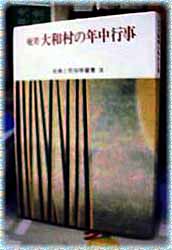 奄美大和村の年中行事
奄美大和村の年中行事古典と民俗学叢書IX
編:古典と民俗学の会
白帝社・昭和60年11月15日初版発行
B6・P198・\1,500
私が生まれたシマ、笠利町川上というところは割と歴史の浅い(薩摩藩支配以後に開墾されたと聞きました)所らしく、さらに生まれてすぐに名瀬に移り住んだため、年中行事というものをほとんど知らずに育ちました。
それでも八月踊りだけは別格で、夏には各郷友会(出身者の集まり。川上郷友会とか)が公園で八月踊りをやったり、あまみ祭りのパレードの晩は支庁通りに繰り広げられる踊りの円は圧巻です。平瀬マンカイとかショチョガマも有名な祭り(儀式?)です。
ところが、この本の内容からはまさに神と共に住むといった印象をうけます。これだけ行事があって仕事が滞らないのかと考えてしまうのは現代の生活基準で考えるからなんでしょうね。
この本は古典と民俗学の会のメンバが昭和57年から数回にわたっての調査をまとめたもので、恵原義盛さんも寄稿しています。主な項目は「年中行事の基層」「年中行事の構造」「年中行事の現況」「調査報告」で、(例によってななめ読みですが)「ハブと年中行事」では大和村での生業暦が掲載されています。そして各時期の作業でハブの被害に遭わないための呪文とか他地域を含めてのハブ除けの日などが掲載されていて、興味深いです。「神の時空」では八月行事が行われる期間がコンパクトにまとめられていて、シマの世界観の図などもあって参考になります。
各項目の末尾には参考とした資料も添付されています。
(mizuma)